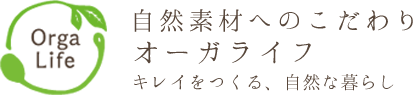「花祭り」をご存じでしょうか?
毎年4月8日に寺院や仏教系の学校で催されている「花祭り」は、お釈迦様の誕生日を祝う仏教の大事な行事のひとつ。
本記事では、この花祭りと、祭りで用いられる甘茶について詳しく紹介します。
花祭りとは?

花祭りとは、冒頭でも説明したように、お釈迦様の誕生日を祝う仏教の大事な行事のひとつです。
灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(ごうたんえ)、浴仏会(よくぶつえ)などさまざまな名称があり、祭りでは花御堂に置かれたお釈迦様の誕生物像に甘茶をかけるのが慣習となっています。
仏教では花祭り以外にお祭りと名の付く行事がありません。
それだけ重要な行事ということですね。
花祭りはお釈迦様が生まれたとされるインドで始まり、その後中国を通じて日本に伝わったと考えられています。
日本で最初に花祭りが行われたのは、聖徳太子の活躍で知られる606年。
その後、奈良時代には大きなお寺に広まり、平安時代には、お寺の年中行事として一般化しました。
そして江戸時代になると、寺子屋を通じて庶民の間に広がったとされています。
花祭りで行われること

花祭りでは、法要だけでなく、花で飾りつけた花御堂(はなみどう)を作り、その中に誕生仏と呼ばれる仏像を安置します。
この誕生仏に柄杓ですくった甘茶をかけるのですが、これはお釈迦様の誕生時に竜が天から降りて、香水(こうずい)を注ぎ、洗い清めたという言い伝えから行われています。
花祭りに甘茶をいただくと無病息災で過ごせるともいわれており、寺院や仏教系の学校では甘茶がふるまわれることも。
平和な世を願い、無病息災を祈るという意味があるお祭りなんですね。
ちなみになぜお釈迦様の誕生日を花祭りと呼ぶのかといいますと、これはお釈迦様の生まれた場所に起因しています。
お釈迦様の母であるマーヤー夫人が出産のために故郷に帰省される際、美しい花が咲き乱れる「ルンビニー園」という花園でお釈迦様が生まれたので、お釈迦様のお誕生日を花祭りと言うんですね。
ノンカロリーでおすすめのあま茶

健康菜茶 あま茶
健康菜茶の国産あま茶は、30年以上農薬や化学肥料を使わない甘茶の栽培に徹底的に取り組んでいます。そんな上質な甘茶を、京都にある提携工場で丁寧にティーバッグ加工・袋詰めを行なっております。
甘茶とは?
甘茶は、ヤマアジサイの変種である小甘茶(こあまちゃ)から作られるお茶です。
小さい花がたくさんついている中央部分を取り囲むように、大きい花がついている不思議な形状をしているのが特徴です。
花は青や紫、ピンクなど色んな色があり、葉は本来とても苦いのですが発酵させると砂糖の100〜1,000倍の甘さになるんだそう。

砂糖がない時代には甘味料として非常に重宝されていたと考えられています。 この甘茶には、
・甘茶で赤ちゃんをなでると、活発で健康な子供に育つ
・上に立つものが良い政治で世を治め、平和な世が訪れると、甘い露が降る(甘露=甘茶に見立てるという説
・甘茶は老いず死なずの神様の飲み物。
というさまざまないい伝えがあります。

オススメの甘茶は?

花祭りをきっかけに、甘茶を知って飲むようになったという人も多いかもしれませんね。
実はこの優しい甘さのハーブティーである甘茶は、季節のムズムズにも効き目があるとか。
さらに甘いものを控えているダイエッターにも近年人気を集めている健康茶なのだそう。
そんな甘茶の中でも、おすすめはオーガライフの「国産あま茶」。
サポニンやフラボノイドなど甘茶の含有成分をたっぷり含んでおり、 さらにノンカフェイン・ノンカロリーなので健康にも◎
自然な甘さが楽しめる甘茶を、是非一度お試しください。